|
――『草の上の仕事』が公開されてから篠原監督に一本撮って貰おうというオファーは。
篠原:いや全然ないですよ(笑)。ひとつだけ、森田さんの毎回やっている『バカヤロー!』が今度ビデオ映画になるけどやらないかというのがあって。
――ビデオ映画はそれが最初ですか。
篠原:そうです。いわゆる商業ベースとしても初めてですね。
――そのあとは『歪んだ欲望』ですか。
篠原:『歪んだ欲望』の前に『YOUNG & FINE』というのがありまして、『歪んだ欲望』になるんです。
――そのあとですか、『月とキャベツ』は。
篠原:そうです。実は『草の上の仕事』のあとに、次にやりたい企画として『音楽事典』という未だに成立していない企画がありまして、カルテット、弦楽四重奏をやっている女性の話なんですよ。
その時僕は31歳くらいだったので、30歳前後の女の子達っていうのは、例えば結婚するか仕事を続けるかとか、みんなそれぞれいろんな岐路に立っている。それで格闘している様が面白いなあと思って。そういう30前後の女の子を扱った映画っていうのはあまりないなあと思いまして。以降いっぱいそういうのが出てくるんですけど。
これは時代的にもあまりないし、クラシック音楽をみんなやっているというのは目新しいし、企画としては面白いんじゃないかと勝手に思いまして、僕は1人で書くより何人かでやったほうがよいので、ほかに2人の人を誘って、3人で台本作り始めて、いろんなところに売り込んでいったんですね。
そんな中で、後に『洗濯機は俺にまかせろ』を製作するボノボって会社があるんですけど、そこの笹岡幸三郎さんというプロデューサーが乗ってくれて、印刷稿という形で台本までは作ってくれまして。それで売り込みをかけてくれて、エースピクチャーズという、現在のアスミックエースが乗ってくれて、両者でどういう風に製作をしようかってとこまでいったんです。
だけどそれ以上のお金が集まらなかったのと、僕は弦楽四重奏なので、本物のプロの演奏家に出演してもらって、演奏プラス芝居をさせるというのをもくろんでたんですけど、なかなか4人見つからなかったんですよ。それに見つかってもお金を出す側からすれば、役者としては素人ですから、素人4人に主演させるというそんな大胆なことはできないと。そんなことがあって、なかなかそれ以上進まなかったんです。
そうこうして、僕はビデオ映画を撮ったりしてるうちに、アスミックの吉田佳代さんというプロデューサーが、『音楽事典』はちょっとできないけど、さっぽろ映像セミナーという、若手のシナリオライター達が集まって企画をやっているのがあって、会社としても実現させたいと。それでその第2回さっぽろ映像セミナーの作品の中で気に入った物があったら一緒にやらないかと、そういう誘いを受けまして。
それで僕はその作品を全部読んで、『月とキャベツ』の元となった『眠れない夜の終わり』というのと、井坂聡さんが『Focus』というタイトルで撮った『起承転転』という、その2本だったら映画化できるんじゃないかという風に打診したんです。
アスミック側も映画化するならその2本と思っていたらしいんで、どっちがやりたいと言われて、僕は『眠れない…』の方をやりたいと。それで吉田佳代さんも『眠れない…』がいいと思っていたので、鶴間香さんていう作者の方に会いに行ったり、映画に立ち上げるためにいろいろやってたんですけど、あんまりうまく行かなくて、これも駄目かってとこまで行ったんです。
実を言うと幽霊物語っていうのは僕のジャンルの中に全くなかったんですよ。幽霊物を作ろうっていうのがなかったんです。
――『歪んだ欲望』は少しそんな感じがありましたが。
篠原:あれもあの時に初めて二重人格物というジャンルを与えられて、どう料理したらいいんだろうと僕なりに考えた挙句、やっとできたみたいなものはあって。
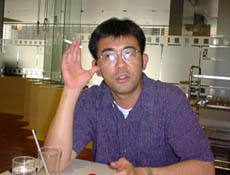 僕は『草の上…』以降、『音楽事典』という作品で挫折してから、既成の作り方というか、枠組があった中でどうやってストーリーを映像化するのかっていうことを初めて考えるようになったんですよ。『草の上…』の時には、脚本の起承転結なんかはどうでもいいんだよっていう流れで作ったんですけど、以降の長編では、ちゃんと物語が組まれている中で普通に語らない方法があるんじゃないかってことを考えながらやっていたんです。 僕は『草の上…』以降、『音楽事典』という作品で挫折してから、既成の作り方というか、枠組があった中でどうやってストーリーを映像化するのかっていうことを初めて考えるようになったんですよ。『草の上…』の時には、脚本の起承転結なんかはどうでもいいんだよっていう流れで作ったんですけど、以降の長編では、ちゃんと物語が組まれている中で普通に語らない方法があるんじゃないかってことを考えながらやっていたんです。
それで『月とキャベツ』の時にそれなりに幽霊物は研究しまして。だいたいああいうものの文法としては、最初に主人公が幽霊であるということを観客にわからせた上で、主人公が幽霊であるってことを知らない人と主人公の葛藤がいろいろあって、そこがコメディ的に面白かったりするのが一つの方法論としてあるなと。
でも鶴間さんの『眠れない…』は最初に幽霊であるということがわからない話だったのが面白くて。僕にとっては鶴間香さんという人が捉えようとした空気感、花火と理人、花火とヒバナとかっていう関係の中で生まれる空気みたいな物が面白かった。これを映画にしたいと思ったんですよ。最後に幽霊であるというのは刺身のつまのようなものだと、そんな風に考えて、最初に考えたプロットはそういうのは無視したような形で進んでたんです。
だけど、幽霊談であるってことがかなり重要なキーワードじゃないのか、これじゃちょっと違うんじゃないかという意見がアスミックサイドからありまして、吉田佳代から「空気感は重要だけど、もう一度幽霊であるってことをちゃんと考えて映画を作ろうよ」っていう風に提示があったんです。
でも僕は幽霊物はお手上げだったので、誰か新たに組めるライターの方がいないかなと考えたら、僕の身近にキャラメルボックスの人達がいて、そういえばキャラメルの連中はよく幽霊物をやってるなと思って、キャラメルの真柴あずきさんに脚本を頼んだんです。
――ロケ地選びはどのような感じで。
篠原:真柴さんに脚本を書いてもらっている間に、場所探しやキャスト探しを並行してやっていたんです。
鶴間さんの脚本では花火はマンションに住んでいたんです。マンションにこもってる不眠症のミュージシャンという設定で。そこに死の床につけないという意味での眠れない少女が夜な夜な現れて、という話だったんです。
それは空気感はいいんだけど、映画にするのにマンションの一室っていうのはあまりにもロマンがないなと思って。自分では川の近くかなというイメージがあって、東京近郊から始まっていろいろ探したんだけどなかなか見付かんなかったんです。
その過程でのちに『洗濯機は俺にまかせろ』の脚本を書く松岡周作君が共同していろいろやっていくようになりまして、松岡君はその前の年に小栗康平さんの『眠る男』に製作担当として参加してたんです。それで彼が群馬の中之条町とは『眠る男』の時にいい関係ができていると。「東京近郊で求めている場所が見付からないなら1回行ってみないか」と言うので行ったんですよ。
そしたら中之条の人達が凄く協力したいと言ってくれまして、ロケハンが始まって、その中之条界隈でいい場所が見つかりまして。それは廃校だったんですけど、ここだって思って。
松岡君と、美術監督の都築雄二さんと3人でその廃校に泊まって、山崎まさよし君にはもう出会っていたんですけど、山崎まさよしがこの廃校で何をしてるかとか、いろんなこと考えてたら、群馬っていうのはキャベツ畑が多いんだよなと。じゃあ山崎まさよしはキャベツを作ってるっていうのはどうだろうと、そんなアイディアが雑談の中で生まれたんです。ミュージシャンが音楽が書けない傍ら何をしているかっていうのはテーマだったんで、キャベツを作るという要素をいれて。
それでその廃校の校庭に木を植えて、草を生やして、塀を作って家のようにして、理人と友人がたまに遊びにきて、そこにヒバナという女の子が現れて、居着いちゃうと、そういう話にしようと。また真柴さんの脚本からまたガラッと変わったんですけど、そこから僕が脚本を引き継いで映画に至ったんです。
――山崎さんは演技の方は初めてだったんですか。
篠原:ええ、CDはもう出していましたが、演技者としては全く初めてでしたね。
――でも自然な演技でしたね
篠原:そうですね。オーディションの時は、彼はあくまで不器用だし、芝居はうまくないなという感じだったんです。でも、なんかある感性が凄いなと。自分の言葉でいろんなことを喋ってくれるんじゃないかと。それと彼の持っている雰囲気というか表情というか、それが凄い強いものがあったので、主役としていけるんじゃないかと直感のようなものがあって、アスミックサイドに投げかけたんです。
一体誰だっていうのは当然あったんですけど、思い切ってやってみろよということで。だからお客が入るとか入らないってことよりは、会社としては作ることに意義があったんじゃないかとは思ってるんですけど。
――ニフティの方では凄い評判よかったですね。巷でも結構話題になったり。キャベツステーキっていうのはなんだっていう話もありましたが(笑)。
篠原:あれも、キャベツを使うネタを色々考えてく中で、キャベツをステーキにして食べたらどうだろうって僕がちょっと思いついたもので、ちょっと助監督に作り方調べられないかって言って、調べてもらったんですよ。
――撮影中には実際には食べられたんですか。
篠原:しょっちゅう食べてましたよ、もうキャベツは山のようにあったので(笑)。もう深夜になるとキャベツステーキだって。あれは簡単にできるものですから。
――『草の上…』の太田光さんもそうですけど山崎さんもこの映画のあとに非常に有名になられましたね。
篠原:偶然そうですね。だからなんか不思議だなって思ってるんですけどね。
| 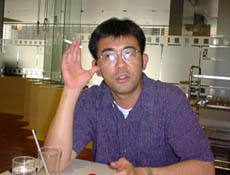 僕は『草の上…』以降、『音楽事典』という作品で挫折してから、既成の作り方というか、枠組があった中でどうやってストーリーを映像化するのかっていうことを初めて考えるようになったんですよ。『草の上…』の時には、脚本の起承転結なんかはどうでもいいんだよっていう流れで作ったんですけど、以降の長編では、ちゃんと物語が組まれている中で普通に語らない方法があるんじゃないかってことを考えながらやっていたんです。
僕は『草の上…』以降、『音楽事典』という作品で挫折してから、既成の作り方というか、枠組があった中でどうやってストーリーを映像化するのかっていうことを初めて考えるようになったんですよ。『草の上…』の時には、脚本の起承転結なんかはどうでもいいんだよっていう流れで作ったんですけど、以降の長編では、ちゃんと物語が組まれている中で普通に語らない方法があるんじゃないかってことを考えながらやっていたんです。